薬局プレアボイド
-
 薬の飲み方・使い方事例50 誤った服用方法から正しい服用方法に修正したことで症状が改善
薬の飲み方・使い方事例50 誤った服用方法から正しい服用方法に修正したことで症状が改善 -
副作用事例49 服用期間中の電話等での状況確認(フォローアップ)
-
 薬の飲み方・使い方事例48 検査に影響する薬について、服用状況を確認し適切な休止を説明
薬の飲み方・使い方事例48 検査に影響する薬について、服用状況を確認し適切な休止を説明 -
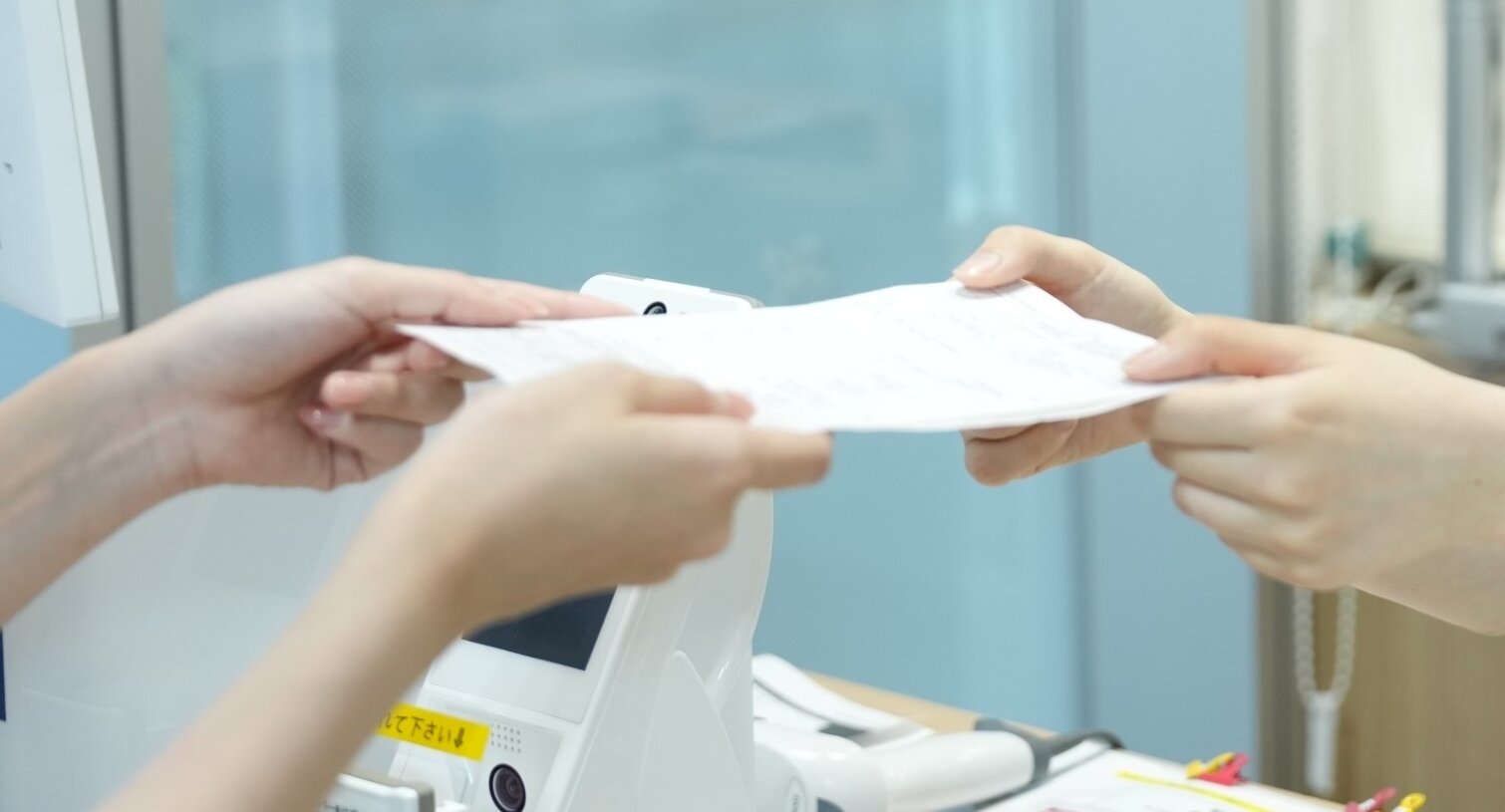 医師との連携事例47 血液検査値から腎臓の機能を想定し、処方中止を提案
医師との連携事例47 血液検査値から腎臓の機能を想定し、処方中止を提案 -
 飲み合わせ事例46 治療継続の必要性について医師に情報提供
飲み合わせ事例46 治療継続の必要性について医師に情報提供 -
 薬の量事例45 在宅医療でのフィジカルアセスメントにより減量を提案
薬の量事例45 在宅医療でのフィジカルアセスメントにより減量を提案 -
 薬の飲み方・使い方事例44 薬の効果が出るまでの時間を考慮して、痛み止めの種類を変更
薬の飲み方・使い方事例44 薬の効果が出るまでの時間を考慮して、痛み止めの種類を変更 -
飲み合わせ事例43 経過観察中の疾患に注意が必要な薬について医師に情報提供
-
薬の量事例42 飲み薬から貼り薬への切り替えにおいて、適切な薬の量を提案


