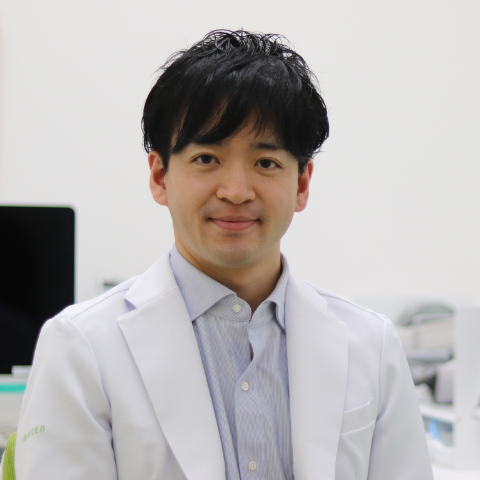自律神経とは、身体を制御する、呼吸、心拍、消化など、私たちが意識しなくても身体の働きを整えてくれる神経です。なんとなく体調がすぐれないと感じるときは、自律神経の乱れが関係しているかもしれません。
今回は、自律神経が乱れる主な原因や乱れたときに出る症状、整えるための具体的な方法などを解説します。
目次
そもそも自律神経とは?
自律神経は、身体の中で自然に働いている神経のことです。例えば、心臓を動かしたり、息をしたり、汗をかいて体温調節できるのは、この自律神経が正常に機能しているためです。
自律神経には、「交感神経」と「副交感神経」の2つがあります。交感神経は、活発に活動するときに働き、副交感神経は、休んでいるときに働いて身体をリラックスさせます。元気でいるためには、この2つの神経のバランスを保つことが重要です。
自律神経が乱れるとどうなるの?
自律神経のバランスが乱れた状態が続くと、「自律神経失調症」と呼ばれる状態になることがあります。動悸(どうき)やめまい、頭痛、胃の不調などが続き、病院で検査をしても原因が特定できない場合に、自律神経失調症の可能性が考えられます。

自律神経失調症にはいくつかのタイプがあり、大きく4つに分けられます。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 本態性自律神経失調症 | 体質的に自律神経が乱れやすい人が発症する。 |
| 神経症型自律神経失調症 | 感受性が強く、体調の変化に敏感な人に多いとされ、心理的な要因で発症する。 |
| 心身症型自律神経失調症 | 最も多いタイプとされ、日常的なストレスをため込むことで発症する。 |
| 抑うつ型自律神経失調症 | 気分の落ち込みや意欲の低下といったうつ症状が目立ち、慢性的なストレスで発症する。 |
中でも抑うつ型は、「うつ病」との区別が難しいとされています。
自律神経が乱れている可能性がないかを確認するセルフチェック項目を用意しました。ふだんの生活を振り返りながら、以下のチェックリストで、自律神経の状態を確認してみましょう。
自律神経セルフチェック項目
- 朝起きてもだるい、眠気が残る
- 日中、急に息苦しくなる
- 頭痛、肩こり、めまいが頻繁に起こる
- 食欲がない、胃腸の調子が悪い
- 寝つきが悪く、夜中に目が覚める
- 手足の冷え、のぼせを感じやすい
- なんとなく気分が落ち込みやすく、やる気が出ない
- 天気や気圧の変化で体調が悪くなることが多い
- 便秘と下痢を繰り返す
- 音や光に敏感になり、イライラしやすい
- 胸がドキドキする
- 手が震えることがある
- 女性:月経不順や更年期の不調がある
あくまで目安であり自律神経失調症を確定するものではありません。当てはまるものが多く、気になる症状がある場合は心療内科もしくは精神科の受診をおすすめします。
関連記事
自律神経が乱れる主な6つの原因
ストレスや生活習慣の乱れは、自律神経に大きな影響を与えます。ここでは、自律神経が乱れる主な6つの原因をご紹介します。
睡眠不足
睡眠中は、自律神経の副交感神経が働き、心と身体をリラックスさせ疲労回復を促します。
スマートフォンやパソコンのブルーライトは、睡眠の質を下げることがあります。ブルーライトを浴びると脳が覚醒するため、副交感神経がうまく働かなくなり、眠りにくくなります。この状態が続くと、自律神経のバランスが乱れ、「疲れやすい」「集中できない」「気分が不安定」などの不調が現れることがあります。
関連記事
食生活の乱れ
身体を動かすエネルギーや神経の伝達に必要な物質は、食べ物から得られる栄養素によって作られています。しかし、コンビニ食や外食、偏った食事が続くと、身体に欠かせないビタミンやミネラルが不足してしまいます。
特に、ビタミンB群は、神経のエネルギー代謝や修復に深くかかわっています。不足するとイライラしやすくなったり、集中力が続かなくなったり、気分が落ち込みやすくなることがあります。
また、マグネシウムや鉄などのミネラルも不足すると、自律神経のバランスに影響を及ぼします。
運動不足
自律神経は、日中の活動時には交感神経、夜の休息時には副交感神経が働くことでバランスを保っています。この切り替えをスムーズに行うために大切なのが運動です。
身体を動かすと、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられます。脳や神経がリラックスしやすくなり、運動後には副交感神経が優位になって、緊張も自然にほぐれていきます。
現代ではデスクワークが増え、意識して動かないと運動不足になりがちです。身体を動かす機会が減ると、自律神経の切り替えがうまくいかず、日中にだるさを感じたり、夜に眠りが浅くなったりすることがあります。
ストレス(精神的・身体的)
ストレスは、大きく分けて「精神的ストレス」と「身体的ストレス」があり、どちらも自律神経に影響をおよぼします。
精神的ストレスには、仕事のプレッシャー、人間関係、不安や緊張などがあり、これらが続くと交感神経が優位になり、副交感神経がうまく機能しなくなります。そうすると、疲れや不眠、気分の落ち込みなどの不調が現れます。
一方、身体的ストレスには、睡眠不足、長時間の同じ姿勢、過労、過度な運動などがあります。身体に大きな負担がかかることで、筋肉の緊張や血流の悪化が起こり、自律神経のバランスが乱れやすくなります。
どちらのストレスも、交感神経を過度に活性化し、副交感神経の働きを抑えることで自律神経のバランスを乱します。長期間続くと、心身の健康に深刻な悪影響を与える可能性があります。
ホルモンバランスの影響
自律神経とホルモンは、どちらも脳の「視床下部(ししょうかぶ)」という部位でコントロールされているため、ホルモンの変動が自律神経に大きく影響を与えます。
特に40~50代の更年期には、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が減少することで、自律神経のバランスが乱れやすくなります。その結果、ほてりや動悸、不眠など、自律神経失調症に似た症状が現れることがあります。
また、月経前に心と身体の調子が不安定になる「月経前症候群(PMS)」も、ホルモンのゆらぎが自律神経に影響することで起こると考えられています。
気圧・気温の変化
私たちの身体は、気圧が下がったり、寒暖差が大きくなったりすると、その変化に対応して自律神経が働き、体温、血圧、呼吸などを調整しています。
近年では、1日の気温差が大きかったり、冷暖房による屋内外の温度差が激しかったりと、身体に負担がかかる環境が増えています。こうした状況では、交感神経と副交感神経の切り替えが頻繁に行われるため、疲れやすくなったり、頭痛、めまい、倦怠感(けんたいかん)、気分の落ち込みといった「気象病」と呼ばれる不調が現れたりすることがあります。
関連記事
今日からできるセルフケア!自律神経を整える方法
なんとなく不調を感じたら、自律神経の乱れが原因かもしれません。セルフケアで、心と身体のバランスを整えましょう。
質の良い睡眠をとる
自律神経を整えるには、質の良い睡眠が欠かせません。夜にしっかり休息できれば、副交感神経が働き、身体がリラックスした状態になります。
質の良い睡眠をとるためには、いくつかの工夫が必要です。例えば、寝る1~2時間前にぬるめ(38〜40℃)のお風呂に入ると、入浴後は体温が徐々に下がり、眠りにつきやすくなります。また、寝る1時間前にはスマートフォンやパソコンなど、ブルーライトを発する機器の使用を控えることも大切です。

さらに、寝室は間接照明でやわらかい光にし、音、室温、湿度にも気を配ると、よりリラックスできます。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣も睡眠の質の向上につながります。
食生活を見直す
自律神経は、神経同士をつなぐ物質やホルモンによって働きが調整されています。これらの材料は、すべて食事から摂る栄養素です。だからこそ、食生活を整えることは自律神経のバランスを保つために欠かせません。
特に意識したいのは、ビタミンB群、マグネシウム、鉄分、タンパク質、ビタミンCなどです。

ビタミンB群は神経のエネルギー代謝や修復を助け、マグネシウムは神経の過剰な興奮を抑えます。鉄分は酸素を全身に運び、タンパク質は神経伝達物質の材料となります。またビタミンCは、ストレスホルモン(コルチゾールなど)の分泌を抑制してくれる働きがあります。
こうした栄養素をバランス良く摂るためには、主食、主菜、副菜をそろえた食生活を心がけましょう。
| 栄養素 | 主な効果 | 主な食材 |
|---|---|---|
| ビタミンB群 | 神経の働きを助ける | 豚肉、納豆、卵など |
| マグネシウム | 神経の興奮を抑える | 豆製品、海藻類、キノコ類など |
| 鉄分 | 酸素を運び疲労を防ぐ | レバー、かつお、小松菜、春菊、ひじきなど |
| タンパク質 | 神経伝達物質の材料になる | 魚類、肉類、大豆製品、卵、乳製品など |
| ビタミンC | ストレスに対する抵抗力を高める | さつまいも、レモン、ブロッコリーなど |
軽い運動やストレッチをする
毎日の生活に軽い運動やストレッチを取り入れると、日中の交感神経と夜の副交感神経の切り替えがスムーズになります。また、運動によって血流が良くなり、脳や内臓に酸素や栄養が届きやすくなるため、神経の伝達も安定しやすくなります。
運動が苦手な方でも、無理なく続けられる軽い運動で大丈夫です。毎日少しずつ習慣にしましょう。
| 運動例 | 目安時間/回数 | 効果的なやり方 |
|---|---|---|
| 軽いウォーキング | 10~20分/1日 | 朝の光を浴びながら、呼吸を意識して歩く。 |
| 就寝前のストレッチ | 5〜10分/1日 | 深呼吸をしながら、首や肩、腰をゆっくり伸ばす。 |
| ヨガ・ピラティス | 50~60分/週2〜3回 | 正しい姿勢で、呼吸を意識しながら行う。 |
| ラジオ体操 | 1回/1日 | 全身を動かすことを意識しながら、リズム良く行う。 |
深呼吸や呼吸法を行う
深呼吸や呼吸法は、自律神経を整えるために手軽で効果的な方法です。特に「吐く息」を意識した深い呼吸を行うことで、副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。ホルモンバランスが一時的に乱れた場合にも有効です。
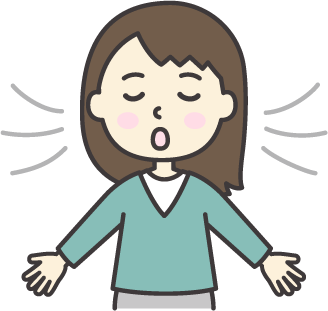
効果的な呼吸法
- 背筋を伸ばして楽な姿勢をとる(椅子に座ってもOK)
- 鼻からゆっくりと(4秒ほど)息を吸う
- 口からゆっくりと(8秒ほど)息を吐く
- これを3~5回繰り返す
ぬるめのお風呂につかる
自律神経を整えるには、ぬるめのお風呂にゆっくりつかる習慣が効果的です。38〜40℃のお湯に10〜15分ほど入ると、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。入浴は血行を促進し、筋肉の緊張をやわらげるため、ストレス軽減にもつながります。
さらに、アロマオイルやハーブを取り入れると、香りのリラックス効果も加わり、自律神経を穏やかに整えられます。

ぬるめの温度での入浴は、ホルモンバランスの乱れによる不調にも効果的です。更年期や月経前のイライラ、不眠、気分の落ち込みなどは自律神経の乱れと関係しており、症状の緩和に役立ちます。
天候の変化を予測して備える
低気圧が近づくと自律神経のバランスが乱れやすく、体調を崩す方が多くなります。予防には、スマートフォンの気象アプリなどで天気や気圧の変化をチェックし、変動が大きい日は無理せず休むことが大切です。
また、気圧の変化による体調不調をやわらげるには、十分な睡眠、水分補給、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
さらに、気温差から身体を守ることも自律神経の安定に役立ちます。脱ぎ着しやすい服装を選び、首や足元、おなかなど冷えやすい部分は特に温めるように意識することが大事です。
冷暖房を使う際は、屋内外の温度差が5℃以内になるよう調整し、急激な温度変化で身体に負担がかからないようにすることも重要です。
セルフケアで改善しない場合は病院へ
自律神経の乱れによる不調は、セルフケアで改善することもあります。しかし、長期間続く場合や症状が強くなる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
似た症状を引き起こす病気として、甲状腺機能異常や貧血、心臓疾患などの身体的な病気や、うつ病や自律神経失調症といった精神的な病気が隠れている可能性もあるためです。
これらは専門的な診断や治療が必要なケースも多く、放置すると悪化する恐れがあります。
そのため、医療機関で問診や血液検査などを踏まえ、適切な治療を受けることが必要です。
小さな習慣が自律神経を整える第一歩
自律神経の乱れは、食生活の乱れ、運動不足、睡眠不足、過剰なストレスなど、日々の生活習慣が大きく関係しています。
バランスの取れた食事、適度な運動、質の良い睡眠などの小さな習慣を積み重ねることが、自律神経を整える第一歩です。
不調を感じたら、無理せず心と身体をいたわる時間を持ちましょう。改善しない場合は医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
参考文献・資料
記事監修
野原 弘義
精神科医/産業医
2014年 慶應義塾大学医学部卒業。
2016年 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 入局。
2018年 製薬会社の統括産業医に就任し、大手金融企業や広告代理店企業などの産業医を務める。
2023年 アインファーマシーズ統括産業医に就任。
スタートアップ企業の産業医にも注力しながら、生活習慣病とメンタルヘルスの方への夜間診療を行うMIZENクリニック市ヶ谷麹町の院長として日々診療に従事している。