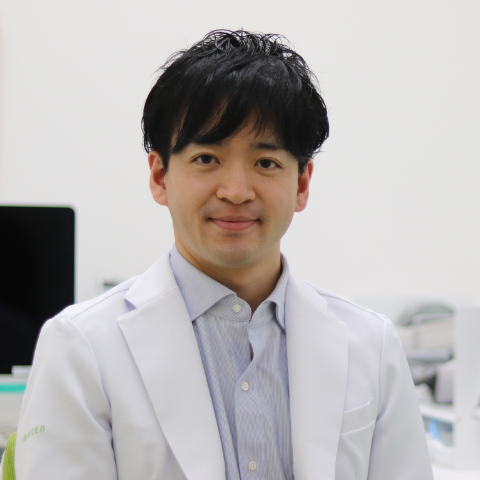アデノウイルスは目・喉・肺・腸などに感染し、感染部位によって異なる症状を引き起こすウイルスです。50種類以上の型があり「プール熱」や「はやり目」などの病名で知られています。飛沫(ひまつ)や接触により感染しやすく、特に子どもは重症化しやすいため注意が必要です。
今回は、アデノウイルスの特徴や感染経路、型ごとの症状、対処法や予防法について解説します。アデノウイルスに感染したらどうしたら良いのか、いざというときに慌てないよう、正しい知識を押さえておきましょう。
目次
アデノウイルスとは
アデノウイルスは目・喉・肺・腸などに感染し、症状の出る部位によって「プール熱」や「はやり目」などさまざまな病名で呼ばれるウイルスです。
「子どもによくみられる感染症」のイメージがありますが、アデノウイルスは大人も感染する可能性のあるウイルスです。大人と子どもで症状に違いはありませんが、多くの大人は抗体を持っているため、症状が子どもと比べて出にくいとされています。
一方、子どもは抗体を持っていない場合も多く、感染すると重症化しやすいため注意が必要です。アデノウイルスはくしゃみなどによる飛沫や接触で簡単に感染が広がります。保育園や学校など集団生活の場では、感染を広げないための対策が重要です。
アデノウイルス感染症の種類と主な症状
アデノウイルス感染症は、症状によって異なる名称で呼ばれています。ここでは代表的な5つのアデノウイルス感染症の種類とその特徴について紹介します。
| アデノウイルス感染症の種類 | 主な症状 |
|---|---|
| 咽頭結膜熱 (プール熱) |
・高熱 ・扁桃腺(へんとうせん)の腫れ ・喉の痛み ・目の充血 ・目やに |
| 流行性角結膜炎 (はやり目) |
・まぶたの腫れ ・白目の充血 ・目やに ・目の異物感 |
| 呼吸器感染症 | ・発熱 ・せき ・喉の痛み ・鼻水 |
| 胃腸炎 | ・おう吐 ・下痢 ・腹痛 ・発熱 |
| 出血性膀胱 (ぼうこう)炎 |
・排尿痛 ・血尿 ・頻尿 ・残尿感 |
ここからは、アデノウイルスの種類別の特徴を見ていきましょう。
咽頭結膜熱(プール熱)
咽頭結膜熱(いんとうけつまくねつ)は、アデノウイルスが原因で起こる感染症のひとつです。夏にプールなどを介した接触感染が多かったことから「プール熱」とも呼ばれますが、冬でも流行することがあります。
幼児から小学生までの子どもに多く見られ、保育園・学校などの集団生活で流行しやすい傾向があります。
主な症状は、39〜40℃の高熱と微熱を繰り返す状態が約5日間続くほか、喉の痛みや扁桃腺の腫れ、目の充血、目やにです。白目が真っ赤になるほど強い充血を伴うこともあります。
医療機関で咽頭結膜熱と診断された場合、外出は控え、自宅で安静に過ごすようにしましょう。学校保健安全法により、症状がなくなって2日を経過するまでは出席停止とされています。
流行性角結膜炎(はやり目)
流行性角結膜炎(りゅうこうせいかくけつまくえん)は、感染力が強く、主に患者の目に触れた手やタオルなどを介した接触感染で広がります。飛沫感染の可能性も指摘されていますが、主に接触感染によって広がると考えられています。
季節を問わず一年を通して発症しますが、特に夏に流行しやすいとされています。
全年齢で発症しますが、特に乳幼児から小学生までの子どもに多く、保育園や学校、家庭内など人との接触が多い環境で感染が拡大しやすい傾向があります。
主な症状として、まぶたの腫れや白目の充血があります。そのほかにも、目が開けられないほどの目やにや涙がたくさん出る、ゴロゴロと異物感が生じるのも特徴です。
片目に感染し、感染した目をこすった手でもう片方の目を触ってしまい、数日のうちに両目に症状が広がるケースも少なくありません。
また目以外にも、耳の前あたりのリンパ節が腫れ、触ると痛みを伴います。発熱や喉の痛みはほとんどみられません。
流行性角結膜炎と診断された場合は、療養中の外出は控え、感染の拡大を防ぐために自宅で安静に過ごしましょう。学校保健安全法では、症状がなくなるまで出席停止とされています。登園・登校時期や再受診の目安は人によって異なるため、医師の指示に従ってください。
呼吸器感染症
アデノウイルスによる呼吸器感染症は、喉や気管支、肺などの呼吸器に感染して発症します。
年間を通して、年齢を問わず感染しますが、冬などかぜが流行する時期に患者数が増加する傾向があります。また主に飛沫感染で広がるため、集団生活をする乳幼児や、免疫力が低下している高齢者に感染しやすいといわれています。
主な症状は、発熱やせき、鼻水、喉の痛みなどがみられますが、症状が長引きやすいのが特徴です。呼吸器症状が軽度であれば自宅での安静が基本です。
しかし悪化すると気管支炎や肺炎に進行し、重症肺炎を引き起こす可能性があるため注意が必要です。まれに脳炎や心筋炎など、命にかかわる重篤(じゅうとく)な合併症を引き起こすこともあります。
そのため、せきや発熱が長引いている・呼吸が苦しい場合は、早めに医療機関を受診しましょう。特に乳幼児や高齢者は重症化するリスクが高いため、家庭内や集団生活内に持ち込まないことが大切です。
胃腸炎
アデノウイルスによる胃腸炎は、季節問わず通年で発症し、接触によって広がります。
特に3歳以下の乳幼児に多くみられる感染症で、主な症状はおう吐や下痢、腹痛です。発熱を伴うこともありますが、熱は比較的軽度であることが一般的です。下痢は1〜2週間ほど長引くこともあり、白っぽくクリーム状の便が出るのも特徴のひとつです。
多くの場合、自然に回復しますが、自宅での安静を基本とし、療養中は水分補給を怠らないようにしましょう。特に乳幼児は脱水症状に注意が必要です。ぐったりしていたり水分を摂れなくなったりした場合は早めに医療機関を受診してください。
出血性膀胱炎
出血性膀胱(ぼうこう)炎は、アデノウイルスに感染することで膀胱が炎症を起こしている状態です。
特に子どもに多いといわれており、排尿時の痛みや血尿、頻繁に尿意を催す頻尿、排尿後も尿が出きっていないように感じる残尿感などがみられます。血尿が出たり、尿に血の塊が混じることもあります。
症状は数日から長いと2週間程度続くこともありますが、ほとんどの場合、自然に改善していきます。ただし尿に血の塊がみられる場合は適切な処置が必要になることもあるため、すぐに医療機関を受診してください。
アデノウイルス感染症の感染経路と潜伏期間
アデノウイルスは、主に「飛沫感染」と「接触感染」の2つの経路で広がります。
飛沫感染
感染者のせきやくしゃみを通じてウイルスが空気中に放出され、それを吸い込むことで感染する。
閉め切った部屋や人との距離が近い場面では、特に注意が必要である。
接触感染
ウイルスが付着したドアノブや手すり、タオル、おもちゃなどに触れた手で、口や鼻、目に触れることにより、体内にウイルスが入り込んで感染が起こる。
小さな子どもがいる家庭や保育施設では、こうした接触感染のリスクが高まるため、特に注意が必要です。
また、アデノウイルス感染症は感染したからといって、すぐに症状が出るわけではなく、それぞれ潜伏期間が異なります。
咽頭結膜熱(プール熱)や流行性角結膜炎(はやり目)では2〜14日、胃腸炎は3〜10日と種類によって異なります。中には2週間近く症状が現れないケースもあります。

発症後の対処法とポイント
アデノウイルス感染症には特効薬がないため、根本的な治療ではなく、基本的に出ている症状をやわらげる対症療法が用いられます。
例えば、発熱やせき、喉の痛み、目の充血、下痢やおう吐などの症状に応じて解熱剤や炎症を抑える薬などを使います。下痢やおう吐がひどい場合は、脱水を防ぐため、こまめな水分補給が必要です。
また、乳幼児や高齢者では、重症化を防ぐために早めの受診が推奨されます。食欲が低下している場合は、消化に良いものを少量ずつ摂るように心がけてください。
喉の痛みがある場合、香辛料など刺激のある食べものや硬いものは、喉を通過する際により痛みを感じやすいため、避けるようにしましょう。
感染を広げないためには、タオルや食器、寝具などを家族と共有せず、できる限り分けて使用します。症状が改善するまで無理をせず、十分な休息をとることも回復への近道です。
アデノウイルス感染症の予防法
主な予防法

主な予防法

アデノウイルスの感染を防ぐためには、日常生活の中でできる予防法を継続的に行うことが大切です。
手洗いやうがいを徹底する
感染予防の基本は、外出先からの帰宅後やトイレ・おむつ交換後、食事前など、こまめな手洗いと丁寧なうがいを徹底することです。
手指に付着したウイルスが目や口を通じて体内に入ることを防ぐため、石けんを使って指先や手首までしっかり洗いましょう。
特に小さな子どもがいる家庭では、家族全員で手洗い習慣を身につけることが大切です。正しい手洗いを意識することで、アデノウイルスだけでなく、ほかの感染症の予防にもつながります。
消毒する癖をつける
アデノウイルスは乾燥した環境でも比較的長く生存します。アルコール消毒が効きにくいため、接触感染の予防には「次亜塩素酸ナトリウム」を用いて消毒しましょう。次亜塩素酸ナトリウムは0.1%のものが効果的とされ、ドアノブやおもちゃ、テーブル、トイレの便座など、手がよく触れる場所の消毒に使われます。
ただし、皮膚に刺激を与える可能性があるため、手指の消毒には適していません。使用の際は、濃度や使用方法に注意しましょう。
感染を広げないためには、こうした場所を定期的に消毒する習慣をつけることが大切です。また、家庭内に感染者がいる場合は、タオルや食器の共有を避けるなど、身近な対策の積み重ねが感染拡大の予防につながります。
せきエチケットを意識する
アデノウイルスはせきやくしゃみによってウイルスを含む飛沫が飛び散ることで感染が広がります。一人ひとりがせきエチケットを意識するだけで、有効な感染対策となるでしょう。
せきやくしゃみが出るときはハンカチやティッシュ、袖で口や鼻を覆い、ウイルスの飛散を防ぎます。マスクの着用も感染拡大の抑制に役立ちます。
特に集団生活をする場では、周囲への思いやりとしてマスクや手洗いと合わせて「せきエチケット」も習慣づけることが大切です。小さな配慮が周囲への感染予防につながります。
免疫力を高めておく
アデノウイルスを完全に防ぐことは難しいですが、感染しても重症化を防ぐには日ごろから免疫力を高めておきましょう。
そのためには、十分な睡眠やバランスの取れた食事、適度な運動習慣を身に付けることが大切です。
特に免疫アップにつながるタンパク質やビタミンD、抗酸化作用を持つビタミンE、腸内環境を整える発酵食品や食物繊維などの栄養素を意識して摂取しましょう。
またストレスをためず、身体を冷やさないよう心がけることも大切です。日常生活を整えることで、感染しにくい身体づくりにつながります。
感染症に負けない環境や身体づくりを目指そう
アデノウイルスは感染力が強く、誰もが感染する可能性があります。乳幼児は特に重症化しやすいものも多いため、日々の予防や健康管理で重症化や感染拡大を防ぐことが大切です。
手洗いや消毒といった衛生習慣に加え、免疫力を高める生活を一人ひとりが意識することにより感染拡大を防げます。
日常的にできることから取り入れて、感染症に強い環境と身体づくりを目指しましょう。
参考⽂献・資料
記事監修
野原 弘義
精神科医/産業医
2014年 慶應義塾大学医学部卒業。
2016年 慶應義塾大学医学部 精神神経科学教室 入局。
2018年 製薬会社の統括産業医に就任し、大手金融企業や広告代理店企業などの産業医を務める。
2023年 アインファーマシーズ統括産業医に就任。
スタートアップ企業の産業医にも注力しながら、生活習慣病とメンタルヘルスの方への夜間診療を行うMIZENクリニック市ヶ谷麹町の院長として日々診療に従事している。